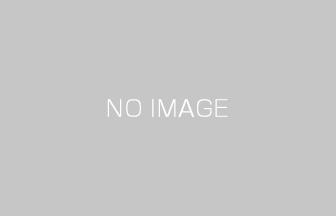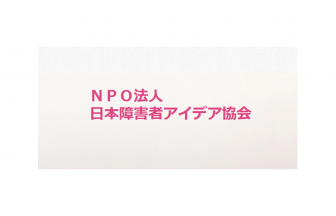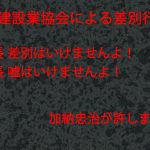『協会名鑑』編集部です。「社会を変える協会特集」第15回は、特定非営利活動法人として活動されている日本ウエルネスダーツ協会様を取材させていただきました!
Q. 日本ウエルネスダーツ協会は、どんな協会なのでしょうか?
ジュニア(小学生)とシニアを対象とした10分割のウエルネスダーツを開発し、普及活動をしています。社会福祉協議会などの行政関連、福祉関連、学校などが主な対象となります。ウエルネスダーツにはフレイルを改善、予防する効果があり、認知症予防、介護予防に利用いただいたり、子どもたちの知育+体育を高めるために利用いただいています。地域コミュニティの活性化にも役立っていると自負しています。

Q. 日本ウエルネスダーツ協会は、どのような想いやきっかけで設立されたのですか?
世界中で認知度の高いダーツですが、日本では酒場スポーツ、ギャンブルスポーツという社会的な認識が強く、競技する場所も限定されている現状です。欧米のように子どもたちやシニア世代が楽しく競技できる環境をつくるべく、オーストラリアで子どもたちに利用されている10分割ボードをもとにして新しいウエルネスダーツ用のボードを開発しました。健康的な環境で容易にダーツを楽しめるようにすることが目的で設立しました。超高齢化社会において少しでも健康寿命を延ばし、認知症や要介護、要支援の状態になることをダーツを楽しむだけで大きな助けになることと確信しています。子どもたちに対しては「早く走れない」「高く飛べない」「太っている」「身体が小さい」など体力的なハンディのある子でもハンディなく競技ができ、礼儀、協調性、集中力などを高めるとともに、計算力や判断力、作戦力を身に着けることが遊びながらできることが大きな特徴となっています。放課後活動、世代交流活動でもご利用いただいています。

Q. 日本ウエルネスダーツ協会は、普段どのような活動をされているのでしょうか?
高齢者には福祉関連施設での体験会、講習会を実施し、その過程で興味を持っていただくことで持続可能なサークル、クラブの設立までを目的としてお手伝いをしています。またモチベーションを保つために大会や交流戦なども設定しています。地域コミュニティの活性化として子供たちや地域住民を交えたイベントも実施しています。体操やウォーキングなどでは少なからず「やらされている感」があったり、強い意志が必要であったりしますが、ウエルネスダーツはゲームを楽しむだけでいいのが持続できることの要因です。競技は基本的に3人のチームで行います。その際にも障がい者や子供たちがなんのハンディなく入ることになります。社会連携、地域連携で協働してもらっている大学生が入ることもありますが、同条件の競技で若さの有利性もあまりありません。参加者みんなが一投一投に歓声を上げる楽しさが、協議を続けていただけることに繋がっています。

Q. 最後に『協会名鑑』読者の皆様へメッセージがありましたらお聞かせください。
独居老人や高齢者だけの家庭も増え続けています。近所同志のつながりも薄くなっているのが現状です。ぜひコミュニケーションのツールとしてでもウエルネスダーツを利用してください。少人数でも大人数でもウエルネスダーツは楽しめます。天候にも左右されません。時間も自由度があり、場所も大きなスペースを必要としません。ウエルネスダーツのボードは重さ500g弱でカレンダーの重さと変わりません。壁にも、ドアにも容易に設置でき、持ち運びも簡単です。ダーツの矢も先端は安全なプラスティック製です。福祉関係やまちづくり関係のNPOやボランティアグループの皆さまにも是非ツールとしてご利用いただければと考えています。